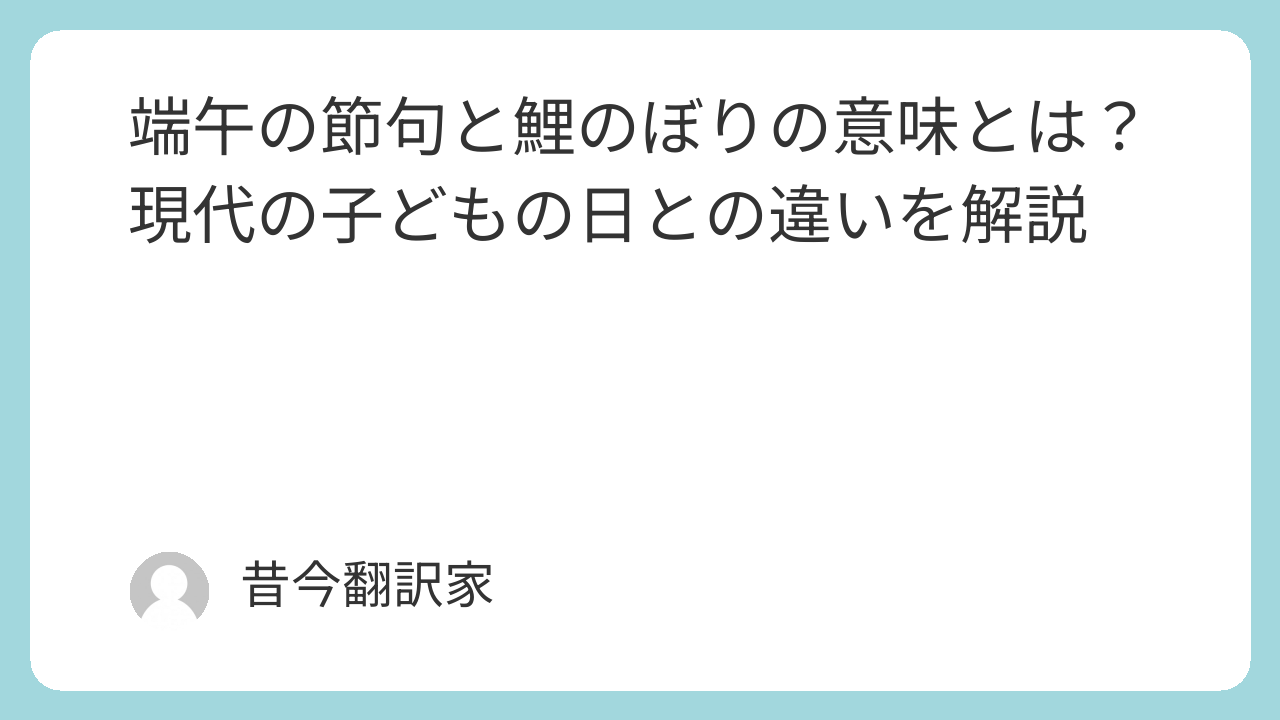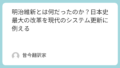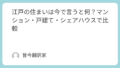五月晴れの空に鯉のぼりが泳ぐ季節になりました。
端午の節句は日本の伝統行事として親しまれていますが、その起源や意味を正確に知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。
実は端午の節句、元々は男の子のお祭りではなく、中国から伝わった季節の変わり目の厄除け行事だったのです。
本記事では、端午の節句の本当の起源から鯉のぼりの由来、そして現代の「こどもの日」との違いまで、この伝統行事の奥深い魅力と変遷をわかりやすく解説します。
日本文化の豊かさを再発見しながら、現代の生活にも取り入れやすい端午の節句の楽しみ方もご紹介していきましょう。
この記事でわかること
- 端午の節句の本当の起源と、なぜ男の子のお祭りになったのか
- 鯉のぼりが立身出世の象徴になった意外な理由
- 現代の「こどもの日」と伝統的な端午の節句の違い
読むのに必要な時間:約7分
端午の節句って何?そもそもの起源は?
「端午の節句」という名前を聞くと、鯉のぼりや五月人形を思い浮かべる方が多いでしょう。
でも実は、端午の節句は元々男の子のお祭りではなかったんです。
端午の節句の「端午」とは「月の初めの午(うま)の日」という意味で、5月5日に定着したのは中国の影響です。
中国では古くから、5月は今で言う「疫病が流行るシーズン」と考えられていました。
つまり端午の節句は、元々は季節の変わり目に身体の健康を願う行事だったんです。
日本に伝わったのは奈良時代(710年〜794年)頃。
当時は宮中行事として菖蒲(しょうぶ)を用いた厄除けの儀式が行われていました。
「菖蒲」の「尚武(しょうぶ)」(武を尊ぶ)という言葉との語呂合わせから、次第に武家社会で男児の成長を祝う行事へと変化していったのです。
現代で例えると、バレンタインデーが本来は聖人を祝う宗教行事だったのに、日本では「男性にチョコを贈る日」に変化したような現象と似ています。
文化が伝わる過程で、その国の事情に合わせて意味が変わっていくんですね。
ここまでのポイント
- 端午の節句は元々中国の季節の変わり目の厄除け行事
- 日本では武家社会の影響で男の子の成長を祝う行事に変化
- 「菖蒲(しょうぶ)」と「尚武(しょうぶ)」の語呂合わせが関係している
なぜ鯉のぼりを飾るようになったの?
端午の節句といえば鯉のぼり。空に泳ぐ姿は風物詩ですが、なぜ鯉なのでしょうか?
これには中国の伝説「登竜門」が関係しています。
黄河の滝(竜門)を登り切った鯉は龍になれるという伝説があり、これが「困難を乗り越えて出世する」という意味になりました。
現代で言えば、「難関大学に合格する」「大企業に入社する」「昇進試験に合格する」といったキャリアの難関突破を願う意味合いです。
江戸時代の親は「わが子には立派な武士になってほしい」という願いを込めて鯉のぼりを飾ったんですね。
日本で鯉のぼりが一般化したのは江戸時代後期から。
最初は武家だけのものでしたが、次第に豊かな商人、そして一般庶民へと広がっていきました。
最初は屋内で飾る小さな鯉の吹き流しだったものが、次第に屋外で風にたなびく大きな鯉のぼりへと発展。
「我が家に男子が生まれました!」という一種のお披露目の意味も持っていました。
現代のSNSで「#生まれました」とハッシュタグをつけて赤ちゃんの写真を投稿するような、家族の喜びの公開宣言だったわけです。
ここまでのポイント
- 鯉のぼりは中国の「登竜門」の故事に由来する
- 子どもの「立身出世」への願いを表している
- 家族構成を表し、男児の誕生を祝う意味もあった
武者人形や五月人形はどんな意味があるの?
玄関や床の間に飾られる武者人形や五月人形。
これらは単なる季節の飾りではなく、子どもの成長に対する親の願いが込められています。
五月人形の多くは、源義経や加藤清正などの歴史上の英雄をモデルにしています。
これは現代で言えば、アスリートやノーベル賞受賞者のポスターを子ども部屋に貼るようなものです。
「こんな風に強く賢く育ってほしい」という願いの表れです。
武者人形の鎧兜には、魔除けの意味もありました。
鎧兜は「形代(かたしろ)」といって、子どもの身代わりとなって厄災から守るという意味を持っていたのです。
現代の五月人形は昔より小型化してアレンジも多様化していますが、「子どもの健やかな成長を願う」という根本は変わっていません。
マンションでも飾れるコンパクトなものや、キャラクターをモチーフにしたものまであり、時代に合わせて変化しています。
ここまでのポイント
- 武者人形や五月人形は子どもの身代わりとなる魔除けの意味がある
- 歴史上の英雄を模範として示す教育的な役割も持っていた
- 現代では住環境に合わせてコンパクト化・多様化している
粽(ちまき)や柏餅を食べる理由は?
端午の節句には粽(ちまき)や柏餅を食べる習慣があります。
これらの食べ物にも深い意味が込められているんです。
粽は中国から伝わった食べ物で、元々は楚の国の忠臣・屈原(くつげん)を偲んで食べられていました。
屈原は国が滅びた際に川に身を投げ、その遺体を魚から守るために人々が米を葉で包んで川に投げ入れたという故事があるのです。
日本の粽は中国のものと形が違いますが、邪気を払う「厄除け」の意味
は共通しています。
一方、柏餅は日本独自の食べ物です。柏の葉は「新芽が出るまで古い葉が落ちない」という特徴があります。
これが「子どもが生まれるまで親が死なない」「家系が絶えない」という縁起の良い意味に結びつきました。
現代で例えるなら、企業の「持続可能性」や「事業継続計画」のような考え方です。
家系の継続性を重視した当時の価値観が反映されています。
ここまでのポイント
- 粽は中国から伝わった厄除けの食べ物
- 柏餅の柏の葉には「家系が絶えない」という縁起がある
- 地域によって食べる物に違いがある
現代の「こどもの日」との違いは?
現在の5月5日は「こどもの日」という国民の祝日になっていますが、これは伝統的な「端午の節句」とは少し異なります。
「こどもの日」が国民の祝日として制定されたのは1948年(昭和23年)のこと。
戦後の民主化の流れの中で、「男女平等」の理念に基づき、男の子だけでなく全ての子どもの幸せを祝う日として定められました。
現代企業の「ダイバーシティ&インクルージョン」のように、特定の人だけでなく全ての人を大切にする考え方が反映されているわけです。
国民の祝日法では、こどもの日は「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日と定められています。
伝統的な端午の節句の「男児の成長を祝う」という面だけでなく、全ての子どもの権利や幸福に焦点を当てているのが特徴です。
今でも多くの家庭では端午の節句の伝統を引き継ぎ、鯉のぼりや五月人形を飾りますが、「男の子のため」というよりは「子どものため」という意識が強くなっています。
ここまでのポイント
- 「こどもの日」は1948年に制定された全ての子どものための祝日
- 伝統的な「端午の節句」は男の子の成長を祝う行事
- 現代では男女平等の理念に基づいて意味が拡大している
世界の子どもの日との比較
子どもを祝う日は世界各国にもありますが、日本の「こどもの日」のように古い伝統行事と結びついているケースは珍しいです。
国連が定めた「世界子どもの日」は11月20日で、子どもの権利条約が採択された日に由来します。
これは企業の「ミッションステートメント」のような、理念や目標を示すものです。
世界各国の子どもの日は、その国の歴史や文化を反映しています。
例えば
- 韓国:5月5日「こどもの日」(日本と同じ日)
- 中国:6月1日「児童節」
- メキシコ:4月30日「El Día Del Niño」
- インド:11月14日「子どもの日」(初代首相の誕生日)
日本の「こどもの日」と「端午の節句」が融合しているように、文化的行事と子どもの権利を祝う日が一致している国もあれば、明確に分かれている国もあります。
ここまでのポイント
- 世界各国にも子どもの日があり、それぞれ独自の意味を持つ
- 国連の定めた「世界子どもの日」は11月20日
- 日本のように古い伝統行事と結びついているケースは珍しい
端午の節句で家族ができる現代風アレンジ
現代の住環境やライフスタイルに合わせた端午の節句の楽しみ方を紹介します。
マンションでもできる!コンパクト鯉のぼり
ベランダ用の小型鯉のぼりや、室内に飾れるミニ鯉のぼりが人気です。
SDGsの「持続可能性」にも通じる、場所を取らないエコな選択肢と言えるでしょう。
家族で楽しむ柏餅作り
市販の柏餅も美味しいですが、家族で一緒に手作りするのも思い出になります。
「伝統を学びながら家族の絆を深める」一石二鳥の体験になりますよ。
こどもの成長記録としての「デジタル端午」
毎年のこどもの日に同じ場所で写真を撮り、成長記録として残す家庭も増えています。
SNSの「#こどもの日」「#成長記録」のハッシュタグで共有するのも現代ならではの楽しみ方です。
男の子も女の子も一緒に楽しむ
現代の「こどもの日」は、性別を問わず全ての子どもの日です。
兄弟姉妹みんなで楽しめる行事にアレンジしましょう。
まとめ
まとめると…
- 端午の節句は元々中国から伝わった厄除けの行事が、日本で男の子の成長を祝う行事に変化した
- 鯉のぼりは「登竜門」の故事に由来し、子どもの立身出世への願いを表している
- 武者人形や五月人形は子どもの身代わりとなる魔除けの意味がある
- 現代の「こどもの日」は男女平等の理念に基づき、全ての子どもの幸せを祝う国民の祝日
- 伝統を尊重しながらも、現代のライフスタイルに合わせたアレンジを楽しむことができる
端午の節句は、子どもの健やかな成長を願う日本の伝統行事です。
時代とともに形を変えながらも、「子どもを大切に思う気持ち」という本質は変わっていません。
現代の「こどもの日」も、その精神を引き継いでいます。
家族でこの伝統を楽しみながら、子どもたちに日本の文化の豊かさを伝えていきましょう。
今までの伝統を知り、現代に合わせてアレンジすることで、端午の節句はこれからも日本の大切な文化として続いていくでしょう。