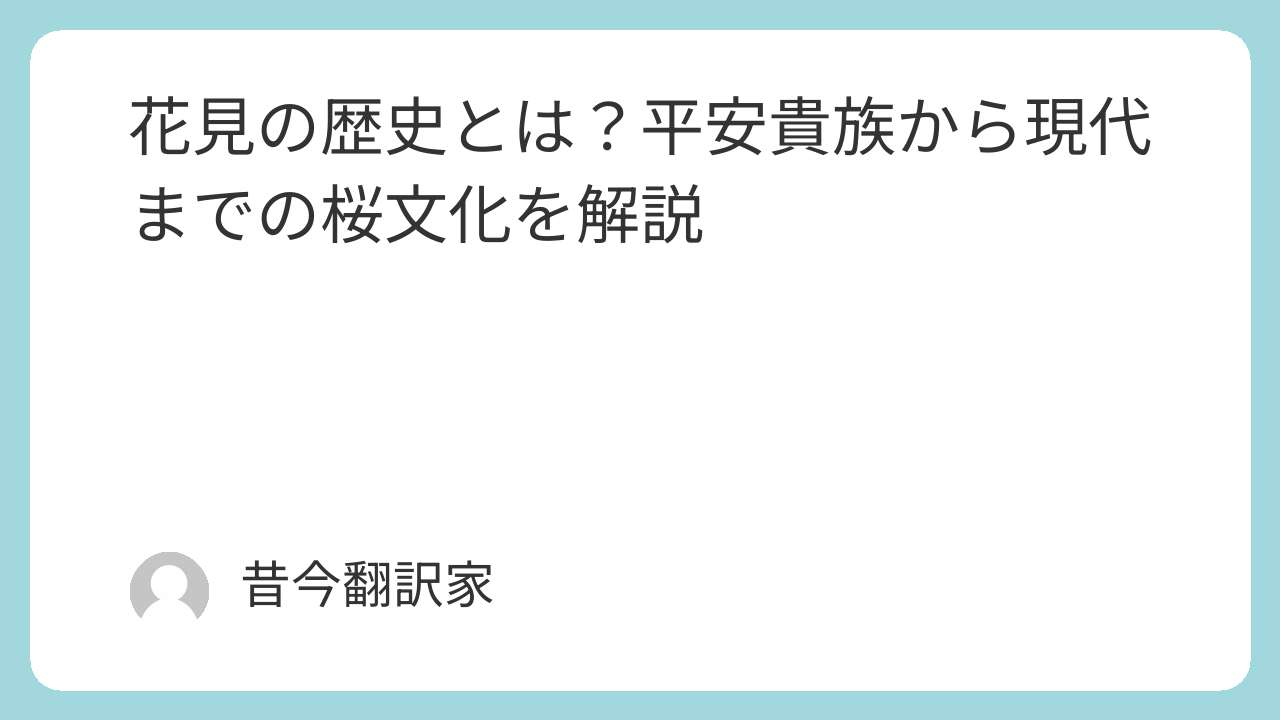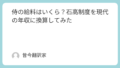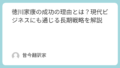「桜を見ながらお酒を飲むなんて日本人らしいよね」、そう言われますが、そもそも花見はどうやって始まったのでしょうか?
実は、最初の花見は桜ではなく梅だったって知っていましたか?
今回は、日本の春の風物詩「花見」の歴史を、平安時代から現代まで、SNSやパーティー文化に例えながらわかりやすく解説します。
花見の起源や変遷を知れば、次の花見がもっと楽しくなりますよ!
この記事でわかること
- 花見がいつから始まり、どのように庶民の文化になったのか
- 時代によって花見スタイルがどう変化してきたのか
- 現代の花見と昔の花見の意外な共通点と相違点
読むのに必要な時間:約8分
花見って元々何のために始まったの?
花見の始まりは、奈良時代(710年〜794年)にさかのぼります。
当時の日本は中国文化を積極的に取り入れていた時代。
最初の花見は桜ではなく梅の花を愛でる行事でした。
これは当時の中国・唐の文化の影響を強く受けていたからです。
今でいうと「海外の流行りモノを取り入れたオシャレな習慣」みたいなものです。
現代人が韓国や欧米のトレンドを取り入れるように、当時の貴族たちは中国の文化的な習慣を積極的に模倣していました。
また、花見には農耕儀式としての側面もありました。
花の開花を見て、その年の農作物の豊凶を占ったのです。
ここまでのポイント:花見は中国文化の影響で始まり、最初は梅が主役。農作物の豊作を祈る実用的な側面もありました。
平安貴族の花見は今で言うとどんなイベント?
平安時代(794年〜1185年)になると、貴族たちの間で梅から桜へと花見の主役が移り変わります。
この時代の花見は、今で言えば「インフルエンサー限定の高級パーティー」のようなものでした。
どんなことをしていたかというと、桜の下で和歌を詠み、酒を飲み、音楽を奏で、貴族同士で交流を深めていました。
現代のSNSでいうと、「インスタ映えする場所で撮影して、その場でポエムを書き、いいね!をもらう」ような感覚に近いかもしれません。
平安貴族にとって花見は単なる遊びではなく、教養と感性を示す重要な社交の場でした。
『源氏物語』や『枕草子』など当時の文学作品にも花見のシーンが数多く登場します。
ここまでのポイント:平安時代の花見は貴族限定の高級社交場で、和歌や音楽を通じて教養を披露する場でした。
なぜ梅から桜に人気が移ったの?
なぜ日本人は梅よりも桜を好むようになったのでしょうか?
それには大きく3つの理由があります。
まず、桜は日本の気候・風土に適していて、国中どこでも見ることができました。
梅が中国から伝わった外来種だったのに対し、桜は日本の国土に自生する身近な花だったのです。
次に、桜の特徴である「一斉に咲いて、はかなく散る」という性質が、日本人の美意識「もののあわれ」に深く響いたからです。
現代でいうと、「限定イベント」や「期間限定商品」に人々が殺到するような心理と似ています。
短い期間しか見られないからこそ、その価値が高まるのです。
第三に、平安時代後期から日本独自の文化を重視する動きが生まれ、中国的な梅よりも日本的な桜が好まれるようになりました。
ここまでのポイント:桜は日本の風土に合い、はかなさが日本の美意識に合致したこと、さらに日本独自の文化を重視する流れの中で人気が高まりました。
武士と庶民の花見はどう違った?
鎌倉時代(1185年〜1333年)から室町時代(1336年〜1573年)にかけて、武士階級が台頭すると、花見の性格も変わっていきました。
武士たちの花見は、今で言えば「会社の公式パーティー」や「企業の記念式典」のような性格を持っていました。
将軍や大名が主催する花見は、家臣団の結束を固め、自らの権威を示す政治的な意味合いも持っていたのです。
一方、戦国時代から江戸時代初期にかけて、花見は次第に庶民にも広がっていきました。
庶民の花見は今でいう「春の行楽」や「野外フェス」のようなもの。
日々の労働から解放されて、みんなで飲食を楽しむ娯楽の場でした。
ここまでのポイント:武士の花見は権威と結束を示す政治的な側面があり、庶民の花見は日常からの解放と娯楽を兼ねた春の行事でした。
江戸時代、花見はどんな感じだった?
江戸時代(1603年〜1868年)、特に元禄期(1688年〜1704年)以降、花見は完全に庶民の文化として定着します。
江戸幕府の第8代将軍・徳川吉宗が1720年代に江戸各所に桜を植樹したことで、花見スポットが増加。
庶民も気軽に花見を楽しめるようになりました。
江戸時代の花見は、今でいう「大規模な野外パーティー」や「フードフェスティバル」に近いものでした。
屋台が出て、酒が振る舞われ、歌舞音曲で賑わう、まさに「お祭り」の様相を呈していました。
現代の「シートを敷いて酒を飲みながら桜を眺める」というスタイルは、基本的にこの江戸時代から続く花見の形です。
歴史上の連続性を考えると、私たちは江戸時代の人々と同じ感覚で花見を楽しんでいるとも言えます。
ここまでのポイント:江戸時代に現代に近い「宴会形式の花見」が庶民文化として完全に定着し、多くの花見名所が整備されました。
明治以降の花見文化はどう変わった?
明治時代(1868年〜1912年)に入ると、花見文化にも変化が生じました。
この時期に現在最も一般的な桜の品種「ソメイヨシノ」が全国に広まり、花見の風景が統一されていきます。
また、明治政府は桜を「国花」として位置づけ、国民統合の象徴としても活用しました。
これは今でいう「ナショナルブランディング」のようなもので、桜が日本の国家アイデンティティと強く結びつけられた時代です。
昭和から平成にかけて(1926年〜2019年)、特に高度経済成長期以降は「会社の花見」が一般化しました。
新入社員歓迎会を兼ねた花見は、現代の「会社の飲み会」のルーツとも言えます。
先輩社員が場所取りのために朝早くから公園に陣取る光景は、バブル期に特に顕著でした。
ここまでのポイント:明治以降、ソメイヨシノの普及と国家による桜の象徴化が進み、戦後は会社の親睦行事としての側面が強まりました。
現代の花見と昔の花見、何が同じで何が違う?
令和時代の現代、花見はどのように変化しているのでしょうか?
まず、スマホとSNSの普及により、花見の楽しみ方が多様化しています。
「インスタ映え」する桜の写真を撮影することも、現代の花見の重要な要素になっています。
平安貴族が和歌で桜の美しさを表現したように、現代人は写真や動画で桜の美しさを表現し、共有しているのです。
また、夜桜のライトアップや桜をテーマにしたイベントなど、花見の楽しみ方も多様化しています。
江戸時代の花見小屋は現代のグランピング施設のようなものでしたが、現代では桜を見ながらのカフェやレストラン、クルーズなど、より洗練された花見スタイルも人気です。
一方、シートを敷いて仲間と飲食を楽しむという花見の基本形は、江戸時代から変わっていません。
「会社の花見」は減少傾向にありますが、家族や友人との花見は依然として人気の春の行事です。
ここまでのポイント:現代の花見は伝統的なスタイルを維持しつつも、SNSや夜桜ライトアップなど新しい要素が加わり、より多様な楽しみ方が広がっています。
まとめ
まとめると…
- 花見は奈良時代に中国の影響で始まり、最初は梅が主役だった
- 平安時代に桜が主役となり、貴族の高級社交の場として発展
- 江戸時代に庶民文化として定着し、現代の花見スタイルの原型が完成
- 明治以降はソメイヨシノの普及と国家的象徴化が進み、戦後は会社の親睦行事としても定着
- 現代の花見はSNSや夜桜ライトアップなど新要素が加わりつつも、江戸時代からの伝統を色濃く残している
花見の歴史を振り返ると、「友人や家族と桜を見ながら飲食を楽しむ」という基本は、実は江戸時代からほとんど変わっていないことがわかります。
時代によって花見のスタイルや意味合いは変化してきましたが、「春の訪れを祝う」という本質的な部分は千年以上にわたって続いているのです。
次に花見に行くときは、平安貴族が感じた「もののあわれ」や、江戸の庶民が楽しんだ「解放感」に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
歴史的な視点を持つと、いつもの花見がより一層味わい深いものになるかもしれませんね。