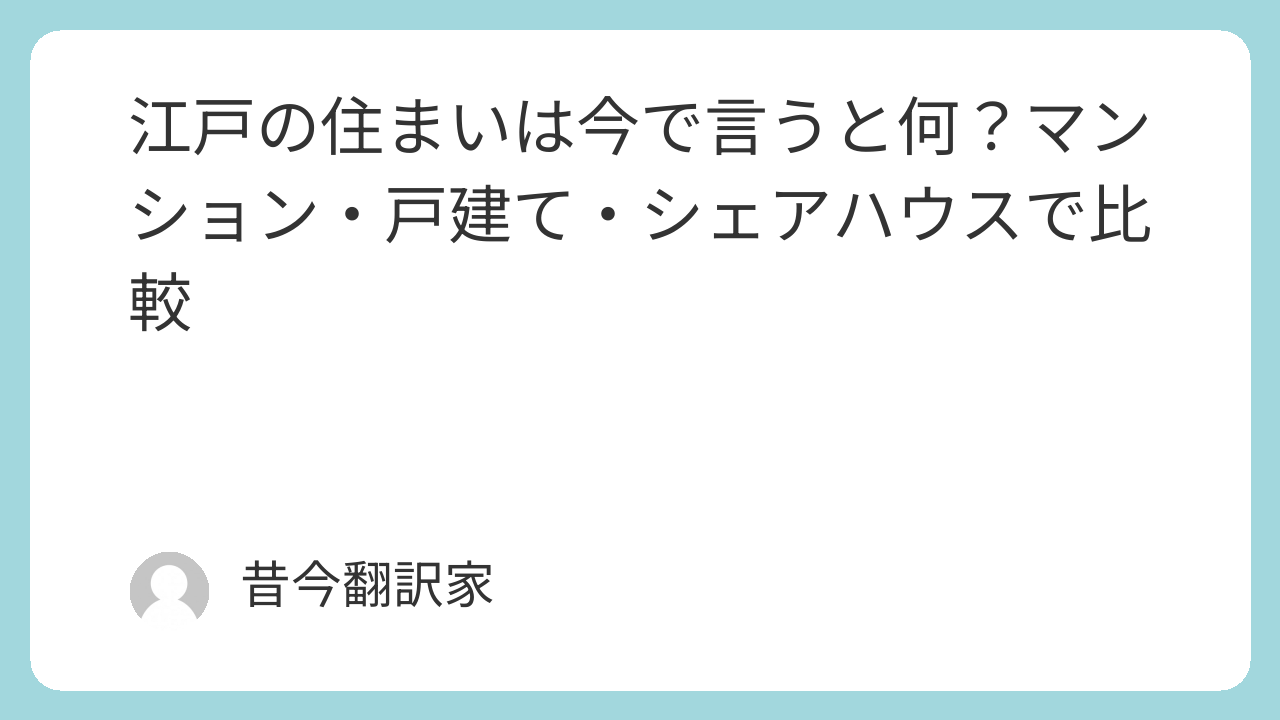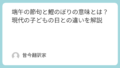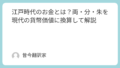「江戸時代の人はどんな家に住んでいたの?」「武士と町人の家って何が違うの?」という疑問を持ったことはありませんか?
実は江戸時代の住まいは、現代の私たちの住居と意外と似ている点がたくさんあるんです!
この記事でわかること
- 江戸時代の住居タイプと現代の住まいの比較ポイント
- 江戸の「階級別」住まいの特徴と意外な共通点
- 当時の住居の工夫が現代にも通じる知恵
読むのに必要な時間:約8分
江戸時代の住居って、どんな種類があったの?
江戸時代の住まいは、住む人の身分や職業によって明確に区別されていました。
主な住居タイプは以下の4つです。
- 武士の屋敷:現代の高級一戸建てや庭付き邸宅に相当
- 町人の長屋:現代のアパートやシェアハウスのような共同住宅
- 商家(店舗兼住宅):今で言う1階が店舗、2階が住居のマンション
- 農家の民家:現代の田舎の一戸建てや農家住宅
江戸の街を上空から見ると、武家屋敷エリアと町人エリアがはっきり分かれていました。
これは現代の「住宅街」と「商業地区」の区分けの原型とも言えるでしょう。
ここまでのポイント
江戸時代の住居は身分制度を反映して明確に区別され、住む場所も限定されていました。
現代の住居タイプと似た機能を持つものが既に存在していたのです。
武士の屋敷は現代で言うとどんな住まい?
武士の屋敷は現代で例えると、高級住宅地の戸建てや、マンションで言えば「タワーマンションの上層階」のような存在でした。
上級武士の屋敷(現代の高級邸宅)
上級武士の屋敷は、現代の「億ション」や大豪邸に相当します。特徴は:
- 広大な敷地と立派な門構え(今で言うと豪邸の高い塀とオートゲート)
- 表門から玄関までの「通り庭」(現代のアプローチや前庭)
- 「表」と「奥」に分かれた間取り(公私分離の元祖!)
- 立派な庭園(現代の高級邸宅のガーデニングスペース)
特に大名クラスになると、江戸時代の上屋敷は現代で言えば「社宅」の役割も果たしていました。
多くの家臣が住み込み、まるで小さな町のようだったのです。
中・下級武士の住まい(現代の一般戸建て)
一方、中・下級武士の住まいは現代の一般的な戸建て住宅に近いものでした。
- 狭い敷地に建つ質素な家(現代の都市部の一般戸建て)
- 家の前に小さな庭(現代の小さな前庭)
- 簡素な造りの門(現代の門扉や玄関ポーチ)
ここまでのポイント
武士の住まいは身分によって大きく差があり、現代の一般住宅から高級邸宅までの幅広いランクに相当していました。
特に上級武士の住まいには、現代の住宅設計にも通じる「公私分離」の考え方が既に取り入れられていたのです。
町人の長屋は江戸時代のシェアハウス?
江戸時代の長屋は、現代のアパートやシェアハウスによく似た共同住宅でした。
壁一枚隔てて別の家族が住む「連棟式住宅」で、現代人の私たちにとって最も身近に感じられる江戸の住まいかもしれません。
長屋のタイプと現代の住まいとの比較
長屋にも様々なタイプがありました
- 棟割長屋:現代のテラスハウスそのもの(壁一枚で区切られた住居が連なる)
- 共同長屋:現代のシェアハウスに近い(トイレや井戸を共同使用)
- 裏長屋:現代の「裏通りのアパート」のような存在
長屋の特徴は
- 1部屋から2〜3部屋程度の狭い間取り(現代の1Kや1DKアパートに相当)
- 共同の井戸や厠(トイレ)(現代のシェアハウスの共有設備)
- 路地を挟んだ向かい合わせの構造(現代の集合住宅の廊下のような共用空間)
長屋の共同生活
長屋での生活は現代のコミュニティ重視型シェアハウスのような面がありました。
- 井戸端会議(現代のSNSやコミュニティアプリのような情報交換の場)
- お隣さんとの密接な関係(現代のご近所付き合いの原点)
- 路地を活用した子どもの遊び場(現代のマンションの公園や広場のような共有スペース)
ここまでのポイント
長屋は単なる住居ではなく、コミュニティ形成の場でもありました。
現代のシェアハウスやソーシャルアパートメントの先駆けとも言える住まい方です。
プライバシーは少なかったものの、人とのつながりが豊かだった点は現代にも見習うべき点かもしれません。
商家は今で言う「職住一体型マンション」?
江戸時代の商家(店舗兼住宅)は、現代の1階が店舗で2階が住居になっているマンションや店舗併用住宅に近い存在でした。
商家の構造と特徴
商家の典型的な間取りは
- 「みせ」(店舗)と「おく」(住居)の二重構造(現代の店舗併用住宅そのもの)
- 「通り庭」(現代の廊下)を挟んで店と住居が並ぶ
- 「座敷」(接客用)と「なんど」(私的空間)の使い分け(現代のリビングと寝室の区別)
- 土間(現代の玄関ホールやエントランス)
特に注目すべきは「表店」と「裏店」の区別です。
メインストリートに面した「表店」は現代のメインストリートの店舗、裏通りの「裏店」は現代の路地裏の小さなカフェやショップに相当します。
職住一体の暮らし
商家の生活スタイルは
- 朝から晩まで仕事と生活が一体化(現代のテレワークやSOHOに近い)
- 家族総出で商売(現代の家族経営の店舗)
- 丁稚・番頭など住み込みの従業員(現代のルームシェアに少し近い)
ここまでのポイント
商家は職住一体の生活を実現した空間で、現代の在宅ワークやSOHOの先駆けとも言えます。
仕事と生活の境界があいまいだった点は、むしろ現代のワークライフバランスの課題にも通じています。
農家の住まいは現代のどんな住居に似てる?
江戸時代の農家は、現代の田舎の広い一戸建てと作業場が一体化したような住まいでした。
農家住宅の特徴
農家住宅の特徴は
- 「土間」と「床上部分」の明確な区別(現代の「土足エリア」と「素足エリア」の区別に通じる)
- 広い土間(現代の作業場やガレージのような空間)
- 「なんど」(寝室)、「ざしき」(接客用)などの複数の部屋(現代の間取り区分の原型)
- 屋根裏や軒下の収納スペース(現代の収納スペースの原点)
特に目を引くのは地域による違いです。
「曲がり家」や「合掌造り」など、気候や風土に適応した様々な形態がありました。
これは現代の地域特性を活かした住宅設計にも通じる知恵です。
自給自足の工夫
農家の住まいには自給自足のための工夫が満載でした
- かまど・いろり(現代のキッチンやダイニング)
- 作業場としての土間(現代のDIYスペースやホームオフィス)
- 農具や収穫物の収納場所(現代の物置やストレージルーム)
ここまでのポイント
農家の住まいは多機能性に優れ、生活と仕事が一体化した空間でした。
現代の複合型住宅やサステナブルな住まいのヒントが詰まっているとも言えます。
江戸時代と現代、住まいの共通点と相違点は?
江戸時代と現代の住まいの共通点
驚くことに、江戸時代の住まいには現代に通じる要素がたくさんありました。
- 身分や収入による住居の格差(現代の高級住宅街と一般住宅街の区別)
- 「表」と「奥」の区別(現代のパブリックスペースとプライベートスペース)
- 環境に配慮した住まいの工夫(現代のエコハウスに通じる知恵)
- 共同体としての住まい方(現代のコミュニティ重視の住宅設計)
江戸時代と現代の住まいの相違点
一方で、大きく異なる点もあります。
- 「個室」の考え方がほぼなかった(現代は家族一人ひとりに個室がある)
- プライバシーの概念の違い(江戸時代は「皆の前で」が基本)
- 設備の違い(トイレ・風呂・台所の位置づけ)
- 家具の少なさ(江戸時代は「空間」重視、現代は「もの」重視)
ここまでのポイント
江戸時代の住まいには現代に通じる合理的な工夫が多く見られる一方、「プライバシー」や「個」の重視度には大きな時代的差異があります。
例えで理解する江戸時代の住まい
江戸時代の住まいを現代の宿泊施設に例えると、こんな感じになります。
- 大名屋敷 → 高級リゾートホテル(広大な敷地、専用の庭園、多くのスタッフ)
- 上級武士の屋敷 → ハイクラスのホテル(清潔で落ち着いた空間、必要十分なサービス)
- 中級武士の屋敷 → ビジネスホテル(必要最低限の機能は揃っている)
- 長屋 → ゲストハウスやホステル(共同設備、親密なコミュニティ)
- 商家 → ホテル兼オフィス(生活と仕事の一体化)
- 農家 → 田舎の民宿(自然と共生、多機能な空間)
まとめ
まとめると…
- 江戸時代の住まいは身分制度を反映した多様な形態があり、現代の様々な住居タイプに通じる特徴を持っていた
- 武士の屋敷は現代の戸建て住宅、長屋はアパートやシェアハウス、商家は店舗併用住宅に相当する
- 江戸時代の住まいには環境適応や空間活用の工夫が満載で、現代の住宅設計にも通じる知恵がある
- 現代との大きな違いは「個室」や「プライバシー」の概念であり、江戸時代は共同体での暮らしが基本だった
- 江戸時代の「土間と床上」「表と奥」といった空間区分は、現代の「パブリックとプライベート」の区別の原点と言える
江戸時代の住まいは、単なる「古い家」ではなく、現代の住居の原型とも言える合理的な工夫が詰まっていました。
特に環境に配慮した暮らしや、コミュニティの中での住まい方は、現代のサステナブルな住居設計や孤立化する住環境の見直しにもヒントを与えてくれます。
江戸時代の人々は限られた資源と技術の中で、最大限に快適な住まいを工夫してきました。
その知恵は400年の時を超えて、私たちの暮らしにも通じているのです。