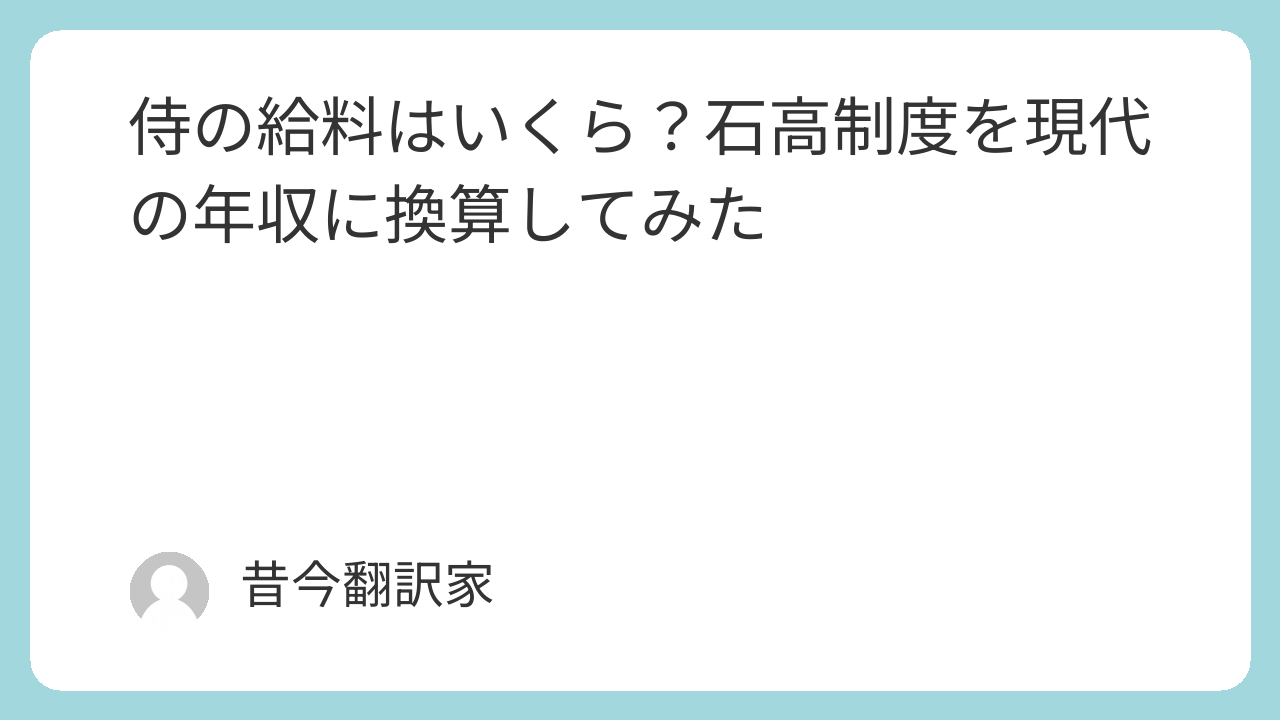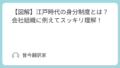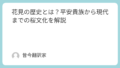「侍って実際どれくらいお金持ちだったの?」
「石高って何?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
実は、侍の給料制度である石高制度は、現代の会社員の年収制度と意外と似ている部分があるんです。
この記事でわかること
- 侍はどのように給料をもらっていたのか
- 石高とは何か、現代のお金に換算するとどれくらいか
- 侍の階級による給料の差と現代のサラリーマンとの比較
読むのに必要な時間:約8分
侍の給料システム「石高制度」ってなに?
江戸時代の侍は、年に数回、米を主体とした「俸禄(ほうろく)」という形で給料をもらっていました。
この給料の額を表す単位が「石高(こくだか)」です。
「石」とは、米1石=約150kgという重さの単位。
例えば「100石の侍」といえば、理論上は年間に米100石(約15トン!)をもらう権利を持つ侍という意味です。
現代の会社で例えると、「年収400万円の社員」というような言い方と同じです。
「あの人は何石取りだ」という会話は、現代の「あの人の年収はいくらくらいだろう」という会話に近いものでした。
ただし注意点として、石高はあくまで「理論上の収入」であり、実際に手に入る米の量は石高より少ないことが一般的でした。
これは幕府や藩の財政事情や、中間マージンのようなものが発生したためです。
ここまでのポイント
- 石高は侍の給料を表す単位で、1石=約150kgの米
- 石高は現代の年収表示に似た概念
- 実際にもらえる量は石高表示より少ないことが多かった
石高を現代のお金に換算するとどうなる?
では、侍の石高を現代のお金に換算するとどうなるのでしょうか?
これには様々な計算方法がありますが、米の価値や購買力を考慮すると、江戸時代の1石は現代の約4〜5万円程度と考えられています。
つまり簡単な目安として
- 10石の侍 → 現代の年収40〜50万円程度
- 100石の侍 → 現代の年収400〜500万円程度
- 1,000石の侍 → 現代の年収4,000〜5,000万円程度
これを会社組織に例えると、10石は派遣社員や契約社員、100石は中堅社員、1,000石は部長クラス、1万石以上は役員クラスといったイメージです。
この換算は完全に正確とは言えませんが、侍の生活水準を現代の感覚で理解する助けになります。
ここまでのポイント
- 1石は現代の約4〜5万円程度に相当
- 石高が10倍違うと、現代の年収でも約10倍の差がある
- 換算方法によって金額は変動する
侍の階級別年収はどれくらい?
侍と一言で言っても、その石高(≒年収)は階級によって大きく異なりました。
一般的な階級別の石高と現代の年収換算を見てみましょう。
- 下級武士(足軽、平侍など)
- 石高:10〜30石程度
- 現代換算:約40〜150万円
- 現代で言えば、非正規雇用や若手社員レベル
- 中級武士(御家人、用人など)
- 石高:50〜200石程度
- 現代換算:約200〜1,000万円
- 現代で言えば、中堅社員から課長・部長クラス
- 上級武士(家老、重臣など)
- 石高:1,000〜10,000石程度
- 現代換算:約5,000万〜5億円
- 現代で言えば、役員や大企業の経営幹部クラス
- 大名
- 石高:1万石〜100万石以上
- 現代換算:約5億円〜数百億円
- 現代で言えば、大企業CEOや大資産家クラス
最も注目すべきは、下級武士と上級武士の間に100倍以上の収入格差があったという点です。
これは現代の企業内の給与格差よりもずっと大きいものです。
ここまでのポイント
- 下級武士は現代の一般会社員より収入が少ない場合も多かった
- 上級武士になると現代の役員クラス以上の高収入
- 武士の間の収入格差は現代の会社組織より大きかった
侍の生活費は?石高で何が買えた?
侍の給料が分かったところで、次は生活費について見てみましょう。
江戸時代の侍の家計では、石高の約70%が食費・住居費・家族の扶養などの基本生活費に使われていたと言われています。
例えば30石の下級武士の場合
- 基本生活費:約21石(現代の約105万円)
- 残り:約9石(現代の約45万円)
この残りで武具の維持、衣服、交際費、冠婚葬祭費などをまかなう必要がありました。
現代のサラリーマンで例えると、年収300万円のうち210万円が生活必需品に消え、残りの90万円で交際費・被服費・趣味などをまかなうような状況です。
特に下級武士は経済的に余裕がなく、副業(内職)をして生計を立てる侍も少なくありませんでした。
これは現代の「副業するサラリーマン」と似た状況です。
ここまでのポイント
- 石高の約70%が基本的な生活費に消えていた
- 下級武士は生活が苦しく、副業をする者も多かった
- 上級武士ほど経済的余裕があった
石高以外の収入源はあった?
侍の収入は石高だけではありませんでした。
現代の会社員が基本給以外に手当やボーナスをもらうのと同じように、侍も「役料(やくりょう)」や「加増(かぞう)」といった追加収入がありました。
- 役料(役職手当)
- 現代の役職手当や職能手当のようなもの
- 重要な役職に就くと、基本の石高に加えて支給された
- 例:城の警備責任者など重要な役職には、数十石の役料が付くことも
- 加増(臨時ボーナス)
- 現代の成果報酬やボーナスのようなもの
- 戦功や特別な功績があったときに与えられた
- 一時的なものと、石高そのものが恒久的に増える場合があった
- 内職(副業)
- 特に下級武士の間で一般的
- 習字・武芸の指南、傘・提灯作り、露天商など
- 現代の「副業するサラリーマン」と同じ発想
ここまでのポイント
- 役料(役職手当)や加増(ボーナス)などの追加収入があった
- 下級武士の多くは内職(副業)で生計を補っていた
- 収入構造は「基本給+α」という意味で現代と似ている
現代のサラリーマンと比べて侍の「待遇」はどう?
最後に、侍とサラリーマンの「待遇」を比較してみましょう。
年収だけでなく、福利厚生や社会的地位なども含めた総合的な比較です。
侍のメリット(現代のサラリーマンと比べて)
- 原則として終身雇用
- リストラや解雇の心配が基本的になかった
- 現代で言えば、かつての日本型雇用の「終身雇用制」の原型
- 社会的地位が高かった
- 武士は身分制度の頂点(士農工商)
- 一般庶民は武士に敬意を示す必要があった
- 現代で言えば、一部上場企業や官庁の「ブランド価値」のようなもの
- 相続可能な職業
- 父親の地位や石高を子が継ぐことができた
- 現代で言えば「ファミリービジネス」のようなもの
侍のデメリット(現代のサラリーマンと比べて)
- 厳格な行動規制
- 服装、住居、結婚相手まで制限があった
- 現代で言えば、超厳格な社内規則と服装規定がある会社の何倍もキツイ
- 転職の自由がない
- 基本的に主君を変えることは難しかった
- 現代で言えば「終身雇用の裏返し」として転職市場がほぼ存在しない状態
- 収入の変動リスク
- 藩の財政難で減給(石高減)されることもあった
- 現代で言えば「会社の業績不振による給与カット」のようなもの
ここまでのポイント
- 侍は終身雇用と社会的ステータスというメリットがあった
- 一方で行動の自由や転職の自由は大きく制限されていた
- 江戸時代後期には武士の経済的地位が相対的に低下した
まとめ
まとめると…
- 石高は侍の給料を表す単位で、1石は現代の約4〜5万円に相当
- 下級武士(10〜30石)は現代の年収40〜150万円程度、上級武士(1,000石以上)は5,000万円以上に相当
- 侍の収入格差は現代の会社組織より大きく、最大で数百倍の差があった
- 石高だけでなく役料(役職手当)や加増(ボーナス)など、現代の給与体系に似た仕組みがあった
- 侍は終身雇用や社会的地位という利点がある一方、行動の自由が厳しく制限されていた
侍の石高制度は、一見すると現代とかけ離れた制度のようですが、よく見ると「基本給+手当+ボーナス」という現代の給与体系の原型とも言える側面があります。
また終身雇用の代わりに転職の自由がないという「日本型雇用」の源流も見えてきます。
歴史上の侍は、単なる「カッコいい戦士」ではなく、当時の「サラリーマン」として日々の生活に奮闘していた姿が浮かび上がります。
特に下級武士の副業事情を知ると、現代の私たちと変わらない「生活の知恵」があったことがわかり、親近感が湧いてくるのではないでしょうか。