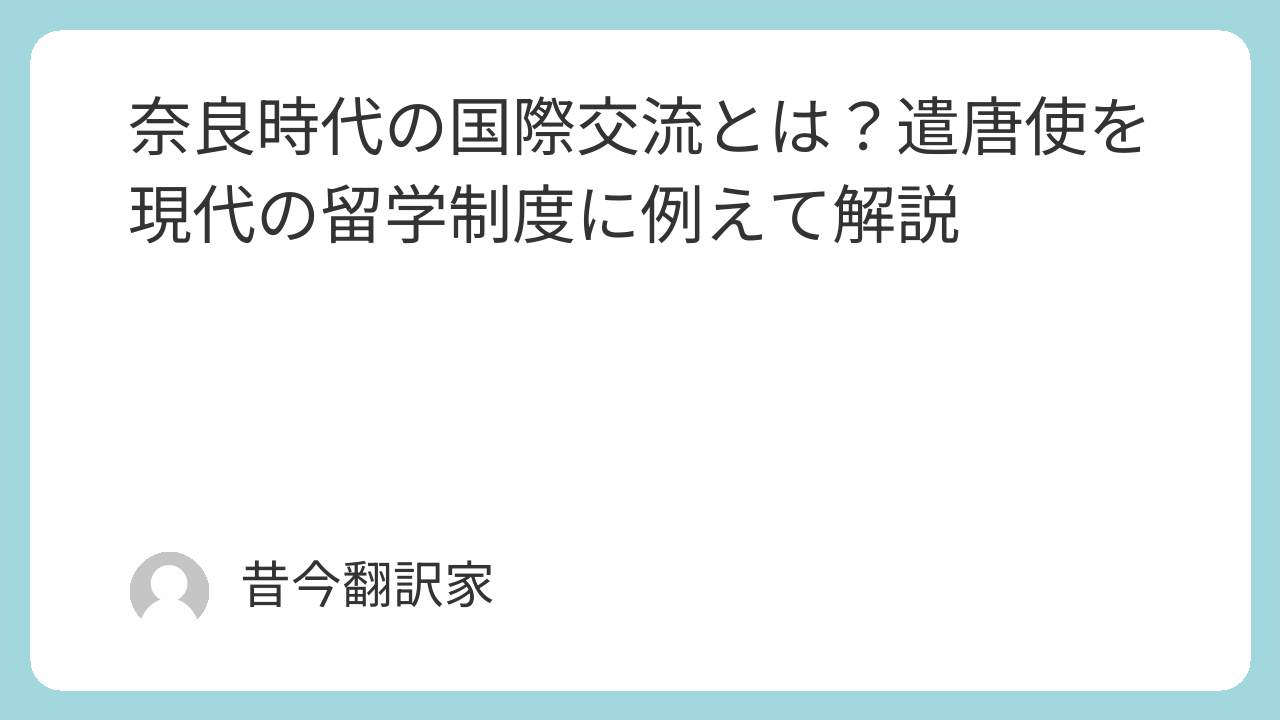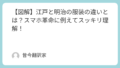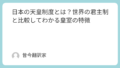「昔の遣唐使って何?」「なんで危険を冒してまで海外に行ったの?」と疑問に思ったことはありませんか?実は遣唐使は、現代の海外留学や企業の海外研修に驚くほど似ているんです!
この記事でわかること
- 遣唐使の役割と目的が現代の海外派遣とどう似ているか
- 奈良時代の国際交流がいかに現代のグローバル化と共通点を持つか
- 命がけの渡航が行われた本当の理由と日本に与えた影響
読むのに必要な時間:約7分
遣唐使って何?現代で例えると?
遣唐使とは、日本から中国(唐)へ派遣された公式使節団のことです。今で言えば、どんな存在なのでしょうか?
現代で例えると「国費で派遣される海外留学生」と「政府の公式外交団」を合わせたような存在です。
文部科学省が派遣する国費留学生や、JICAの海外研修員、外務省の外交官などを一つの使節団にまとめたイメージですね。
遣唐使は630年から894年までの約260年間に、合計16〜18回ほど派遣されました。
特に奈良時代(710〜794年)は海外との交流が盛んで、当時の日本のグローバル化を支えていたんです。
ここまでのポイント
遣唐使は現代の国際交流団や留学生のように、国家の将来のために知識や技術を学びに行った公式使節団でした。
なぜ命がけで海を渡ったの?
当時の日本から中国への渡航は、遭難率が約30%もある危険な旅でした。
それでも遣唐使が派遣され続けたのはなぜでしょうか?
唐(中国)は当時の世界最先端の文明国だったからです。
現代で言えば、IT企業がデジタル技術を学ぶためにシリコンバレーに社員を派遣するようなもの。
あるいは、医学生が最先端医療を学ぶためにアメリカやヨーロッパの有名病院で研修するようなものです。
具体的に日本が欲しかったものは
- 政治制度(律令制度)→ 現代の行政システムや法律体系
- 仏教の最新知識 → 現代の最先端学術研究や哲学
- 建築技術 → 現代の建築工学や都市計画
- 文化・芸術 → 現代のデザインやエンターテイメント産業
現代企業が「技術的負債」を解消するために新技術導入を急ぐように、当時の日本も国際競争に勝つために先進技術の導入を急いでいた>のです。
ここまでのポイント
命がけの旅も、国家の発展と個人のキャリアアップのために価値があったのです。
遣唐使の旅はどんな感じ?今の海外出張と比べると
遣唐使の旅程を現代の海外出張と比べてみましょう。
| 項目 | 遣唐使(奈良時代) | 現代の海外出張 |
|---|---|---|
| 移動手段 | 木造船(30〜40m程度) | 旅客機(全長60〜70m) |
| 移動時間 | 片道3〜4ヶ月 | 成田→北京 約4時間 |
| 危険度 | 非常に高い(遭難率約30%) | 非常に低い(航空事故率は0.0001%以下) |
| 同行者数 | 約500人(複数船に分乗) | 1人〜数人のチーム |
| 滞在期間 | 1〜3年 | 数日〜数週間 |
| 費用 | 国家予算の大部分 | 会社の出張予算内 |
現代のビジネスマンが出張前に航空券やホテルを予約するように、遣唐使も事前に船を建造し、航路を調査し、外交文書を準備していました。
でも規模が全然違います!
現代の海外出張は「行ってきます!」と言って数日後には戻ってくるのに対し、遣唐使は「ご武運を」と見送られ、数年後に「生きて帰れました!」というレベルの大事業だったのです。
ここまでのポイント
遣唐使の旅は現代の感覚では想像できないほど長く危険なものでしたが、組織的にきちんと計画されていました。
遣唐使が持ち帰ったものって?
遣唐使が日本に持ち帰ったものを、現代の例で考えてみましょう。
国家の制度設計図(律令法典)
- 現代例:先進国の行政システムや法律体系のコピー
最先端の知識・技術(医学、天文学、建築技術)
- 現代例:AIやクリーンエネルギー技術の導入
文化・芸術(音楽、絵画、文学)
- 現代例:海外の映画やアニメ、音楽の輸入
流行のアイテム(唐風の衣装、調度品)
- 現代例:海外ブランド品や最新トレンドの取り入れ
現代企業が海外視察で「これは使える!」と思ったアイデアを持ち帰るように、遣唐使も「日本に導入すべき」と思った文化や技術を選んで持ち帰っていました。
ここまでのポイント
遣唐使は単なる親善大使ではなく、国家発展のための具体的な「ショッピングリスト」を持った戦略的な使節団でした。
SNSで例える遣唐使の情報収集術
遣唐使の情報収集方法は、現代のSNSやメディアと比較できます。
長安(現在の西安)での生活は、現代の人がニューヨークやパリに住んでインスタグラムに現地情報をアップするような感覚だったかもしれません。
- 留学生の記録 → 現代のブログや留学体験記
- 僧侶の記録 → 専門家のTwitter発信や学術論文
- 使節団の公式記録 → 公式プレスリリースやニュース報道
特に、円仁の「入唐求法巡礼行記」のような旅行記は、現代のトラベルブログのような役割を果たしていました。
現地の様子や文化の違いを詳細に記録し、読者(朝廷や他の知識人)に伝えていたのです。
ここまでのポイント
遣唐使は情報収集と発信の両方を担い、奈良時代のメディア的な役割も果たしていました。
遣唐使が日本に与えた影響とは?
遣唐使がもたらした影響は、現代のグローバル化による影響と似ています。
- 先進技術の導入
- 現代例:海外IT技術や医療技術の導入
- 文化的多様性の増加
- 現代例:様々な国の料理や音楽が日本に入ってくること
- 国際的な視野の拡大
- 現代例:海外ニュースやSNSを通じた世界観の拡大
- 日本独自のアイデンティティ形成
- 現代例:グローバル化の中での「クールジャパン」のような独自文化の再評価
現代の日本企業が海外技術を「日本流」にアレンジするように、奈良時代も唐の文化を単に真似るだけでなく「日本化」していきました。
これが平安時代以降の「国風文化」につながっていくのです。
遣唐使の廃止(894年)後は、日本独自の文化発展が加速しました。
これは現代で言えば、「海外留学経験を活かしつつ、日本らしさを大切にした新しいビジネスモデルを作る」ような感覚でしょうか。
まとめ
まとめると…
- 遣唐使は現代の国費留学生や企業研修のような「知識技術獲得」が目的だった
- 命がけの3〜4ヶ月の航海と1〜3年の滞在は、現代の海外赴任よりもはるかに大変だった
- 遣唐使がもたらした文化・技術・制度は、日本の基礎を形作った
- グローバル化と国家アイデンティティの形成という、現代日本と共通する課題があった
- 情報収集とその発信という点では、現代のメディアやSNSに通じる役割も果たしていた
奈良時代の遣唐使は、現代の海外留学や研修と目的も役割も似ていました。
違いは、その過酷さと国家戦略としての重要性の大きさです。
今、私たちが当たり前のように享受している「海外の文化や技術」は、1300年以上前から、命がけで海を渡った先人たちの努力によってもたらされました。
現代のグローバル社会を生きる私たちも、彼らの国際交流精神から学ぶことがたくさんあるのではないでしょうか。