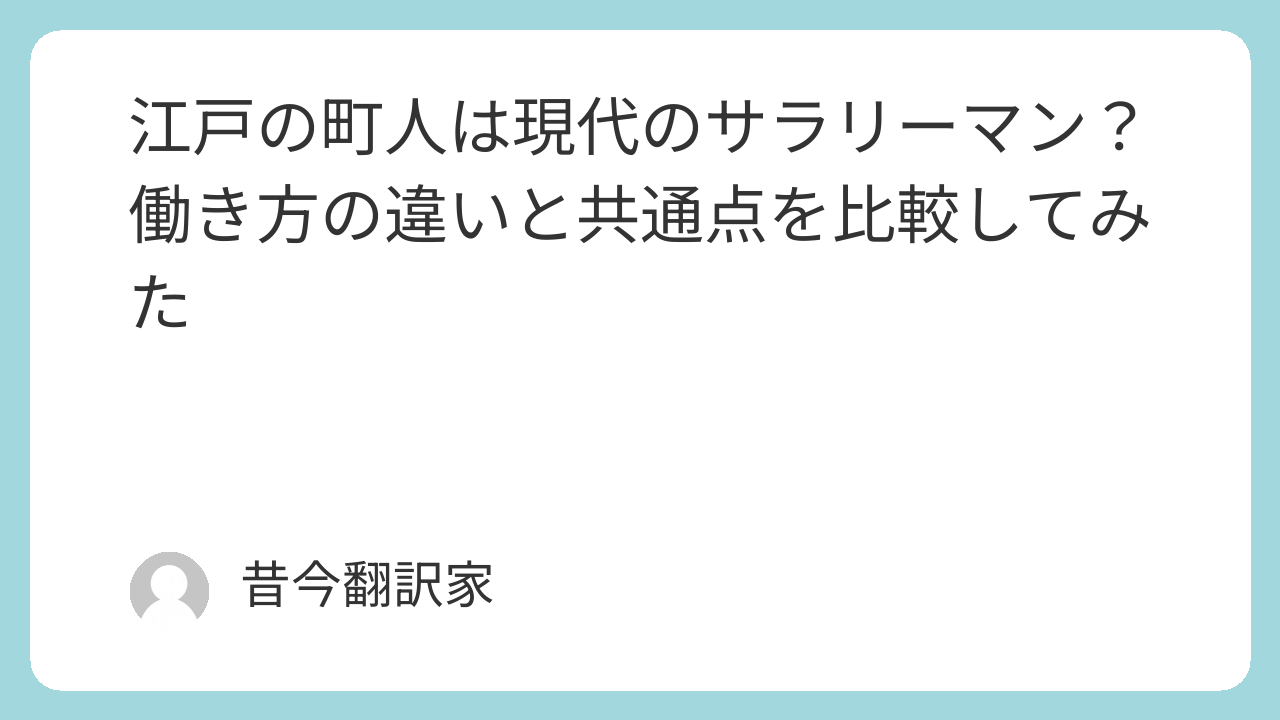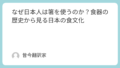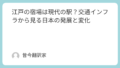「江戸時代の町人って何をしていたの?」「今のサラリーマンとどう違うの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?
実は江戸時代の町人と現代のサラリーマンには、意外な共通点があるんです!
この記事でわかること
- 江戸時代の町人の仕事と生活スタイルがイメージできる
- 現代のサラリーマンとの意外な共通点がわかる
- 江戸時代の「働き方改革」と現代の違いがわかる
読むのに必要な時間:約8分
江戸の町人ってどんな人たち?
江戸時代の社会は、「士農工商」という身分制度で成り立っていました。
この中で「町人」は主に商人と職人を指し、現代の会社員や自営業者に近い存在です。
町人の中でも「商人」は物を売り買いして利益を得る人々で、小さな行商から大きな商家まで様々。
一方「職人」は技術を持って物を作る人々でした。
現代でいえば、商人は「小売店のオーナー」から「商社マン」まで、職人は「技術者」や「専門職」に相当します。
ただし大きな違いは、身分の固定性。江戸時代では生まれた身分から抜け出すのは基本的に難しかったんです。
ここまでのポイント
町人は現代の会社員や自営業者に似た存在で、都市部で商業や手工業に従事していました。
町人の仕事は今で言うと何に当たるの?
江戸時代の町人の仕事と現代の職業を比べてみましょう
- 呉服屋:現代の高級アパレルショップや百貨店の衣料品部門のような存在
- 両替商:銀行やローン会社のような金融業
- 米問屋:食品商社や穀物専門商社
- 魚屋・八百屋:スーパーの生鮮食品部門や専門店
- 家具職人:家具メーカーの技術者やインテリアデザイナー
- 髪結い:美容師・理容師
江戸時代の商人の中には、三井や住友のような大商家も存在し、これらは現代の大企業の起源となりました。
彼らは単なる「商人」ではなく、現代のコングロマリット(複合企業)のような存在だったんです。
ここまでのポイント
江戸時代の町人の仕事は現代の職業に置き換えられます。
中でも大商家は現代の大企業の起源となりました。
江戸時代の「出世」と現代の「キャリアアップ」は似てる?
江戸時代の商家では、「丁稚奉公」から始まるキャリアパスがありました。
これは現代のキャリアステップと比較すると意外と似ているんです。
| 江戸時代の階層 | 現代の役職 | 主な仕事内容 |
|---|---|---|
| 丁稚(でっち) | 新入社員・研修生 | 掃除、使い走り、雑用 |
| 手代(てだい) | 中堅社員・主任 | 実務、現場仕事、記帳 |
| 番頭(ばんとう) | 部長・支店長 | 経営の補佐、重要判断 |
| 暖簾分け | 独立起業・のれん分け | 独立した店舗経営 |
丁稚は今で言えば「研修生」のような存在で、10歳前後で商家に入り、掃除や使い走りなどの雑用をしながら商売の基本を学びました。
真面目に働けば、20歳前後で「手代」に昇進できます。
手代になると実際の商売の実務を任されるようになり(現代の一般社員)、さらに優秀であれば「番頭」に。
番頭は現代の部長や役員のような存在で、店の経営を任されることもありました。
最終的な「出世」の形は「暖簾分け」。主人から独立を許され、同じ商売の店を出すことができるんです。
これは現代で言えば、会社の支援を受けての独立起業や、フランチャイズ店のオーナーになるようなものです。
ここまでのポイント
江戸時代の商家のキャリアパスは、現代の会社組織における出世コースと構造的に似ています。
働く時間はどう違った?江戸時代の「働き方」
江戸時代の仕事時間は基本的に「日の出から日没まで」。時計がなくても太陽を見れば働く時間がわかるという、自然のリズムに合わせた働き方でした。
季節によって労働時間が変わるのも特徴です
- 夏:朝5時頃〜夕方7時頃(約14時間労働)
- 冬:朝7時頃〜夕方5時頃(約10時間労働)
一方、現代のサラリーマンは基本的に1日8時間、週40時間労働が標準です。
江戸時代と比べると、特に夏場は現代人の方が数時間短く働いていることになります。
休日については、江戸時代は「定休日」という概念があまりなく、月に数回の「休み」がありました。
- 六斎市(いちのひ):毎月6回、市が立つ日に休む
- 棚卸や決算の日
- 祭りや行事の日
現代の週休2日制(月8〜9日休み)と比べると、江戸時代の月2〜6日の休みはかなり少なめ。
でも、商売の繁閑に合わせた柔軟な働き方だったとも言えますね。
ここまでのポイント
江戸時代は自然のリズムに合わせた労働時間で、休日は現代より少なめでしたが、状況に応じた柔軟な働き方もありました。
お給料事情〜江戸の商人と現代サラリーマンのお財布事情〜
江戸時代の商家で働く人のお給料事情は現代とかなり違います。
- 丁稚(でっち):基本的に給料なし!代わりに「住居・食事・着物」などの現物支給(現代の「社宅+食費補助+制服支給」みたいなもの)
- 手代(てだい):小遣い程度の給料+賞与(お年玉・盆玉)
- 番頭(ばんとう):給料+利益配分(今でいうインセンティブや業績連動賞与のような仕組み)
江戸時代の丁稚は、10年以上無給で働くことも珍しくありませんでした。
現代の感覚では考えられませんが、「技術と知識を学ぶ」という意味では、超長期インターンシップのようなものだったのかもしれません。
手代になると少額の給料が出るようになり、番頭になると店の売上に応じた取り分があり、現代のマネージャー職のような待遇になります。
最終的に独立して「暖簾分け」を許されると、自分の店を持つことができ、現代で言えば「起業」に相当します。
ここまでのポイント
江戸時代の給料体系は現代と大きく異なり、若いうちは「学び」の対価として無給でも働く文化がありました。
会社組織で例える江戸の商家
江戸時代の商家を現代の会社組織に例えると、こんな感じになります。
| 江戸の商家 | 現代の会社 | 役割 |
|---|---|---|
| 主人(あるじ) | 社長・オーナー | 最終決定権者、全責任者 |
| 番頭(ばんとう) | 部長・執行役員 | 実務責任者、経営の右腕 |
| 手代(てだい) | 一般社員・主任 | 実務担当、接客や記帳 |
| 丁稚(でっち) | 研修生・新入社員 | 雑用、基本を学ぶ |
江戸時代の商家の特徴は「家」単位の経営。
商売と家庭が一体となった「家業」だったんです。
現代のベンチャー企業や家族経営の会社に近いかもしれません。
現代企業との大きな違いの一つは、「住み込み」スタイルであること。
商家で働く人たちは基本的に店舗兼住居である「店」に住み込んで働きました。
現代で例えるなら「社宅と会社が一体化」したような形です。
この「住み込み」スタイルのため、プライベートと仕事の区別があまりなく、24時間勤務のような側面もありました。
一方で、家族のような結びつきが強く、長く勤めた番頭などは「養子」になることもありました。現代の「会社は家族」という考えの原型かもしれませんね。
ここまでのポイント
江戸の商家は「家業」として家族的な結びつきが強く、住み込みで働く形態が一般的でした。
江戸時代の「サービス残業」と「有給休暇」事情
江戸時代の働き方を現代の「労働基準」で見ると、驚くべき違いがあります:
- 残業概念:「残業」という概念自体がなく、必要なら日没後も働くのが当たり前でした(現代風に言えば「みなし労働時間制」のような感じ)
- 休日出勤:繁忙期や特別な日には休日でも働くことが普通
- 有給休暇:現代のような「権利としての休暇」はなく、主人の許可が必要
江戸時代の商家では、「働く時間」と「プライベートの時間」の区別があまりなかったんです。
特に住み込みの丁稚や手代は、仕事終わりでも主人や番頭に呼ばれれば対応するのが普通でした。
一方で、現代にはない柔軟さもありました。
- 商売が暇な時期は自然と休みが多くなる
- 地域の祭りや行事の日は丸一日休みになることも
- 冬場は日が短いため、自然と労働時間も短くなる
現代の「働き方改革」と比べると原始的に見えますが、自然のリズムや商売の繁閑に合わせた「無理のない働き方」という側面もあったのかもしれません。
ここまでのポイント
江戸時代は現代のような労働時間の概念は曖昧でしたが、自然のリズムや商売の状況に合わせた柔軟な働き方がありました。
まとめ:江戸の町人と現代のサラリーマン、変わるものと変わらないもの
まとめると…
- 江戸時代の商家のキャリアパス(丁稚→手代→番頭→暖簾分け)は、現代の会社組織のキャリアパスと構造的に似ている
- 働く時間や休日の考え方は大きく違うが、季節や商売の繁閑に合わせた柔軟さがあった
- 江戸時代は「住み込み」で仕事とプライベートの区別があいまいだったが、家族的な結びつきが強かった
- 商売の基本精神「三で十年(少ない利益でも長く続ける)」は、現代のビジネス倫理にも通じる
- 時代は変わっても「人間関係」「キャリアアップ」「ワークライフバランス」の課題は共通している
江戸時代と現代、約200年以上の時を超えて、働き方には大きな違いがあります。
しかし、「キャリアを積みたい」「適正な報酬を得たい」「やりがいのある仕事がしたい」という人間の基本的な願いは変わっていないのかもしれません。
時代が変わっても変わらない「働くことの本質」を考えると、江戸時代の町人たちの知恵や工夫は、現代の私たちにも示唆を与えてくれそうです。
彼らは厳しい環境の中でも、自然のリズムに合わせ、人間関係を大切にし、長期的な視点で商売を続けてきました。
その精神は、忙しい現代社会を生きる私たちにも、静かに語りかけているように思えます。