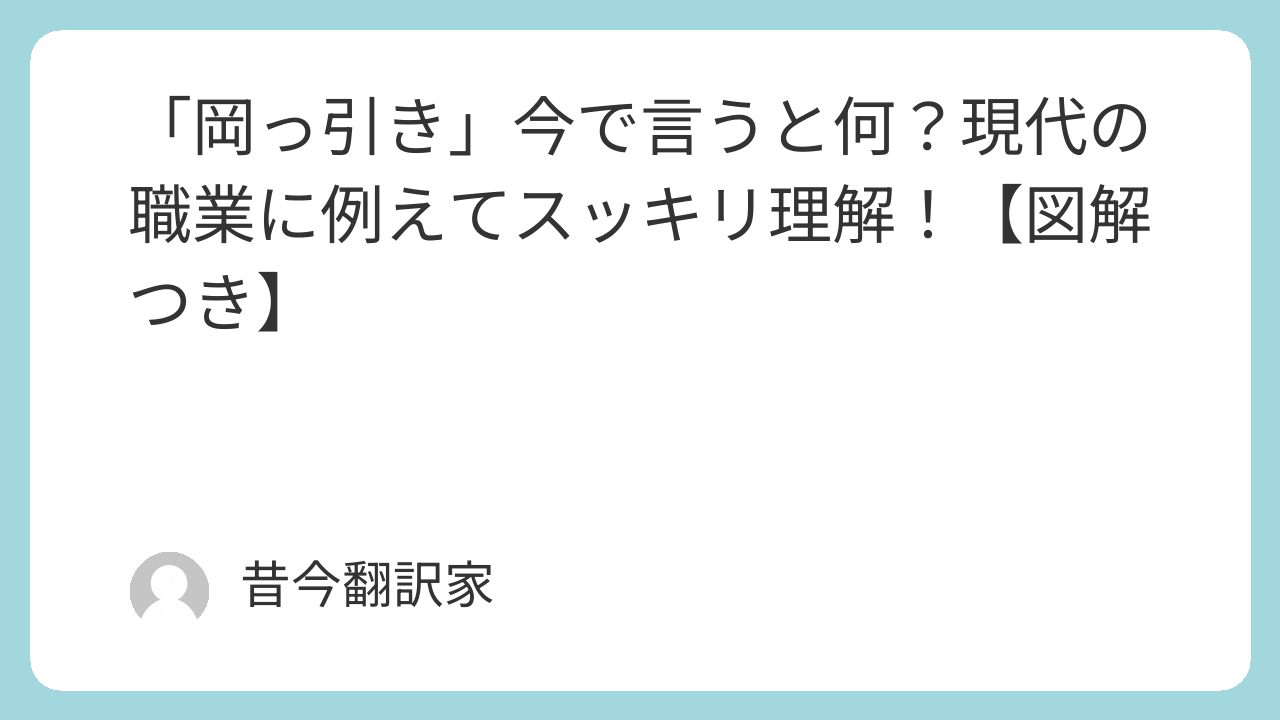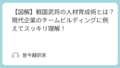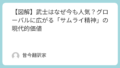岡っ引きは、今で言えば「警察の民間協力者」や「情報提供者」に近い存在です。
江戸時代に町奉行所の同心に雇われ、犯罪捜査や情報収集を手伝っていました。
時代劇で十手を持って走り回る姿は印象的ですが、「結局何をする人?」「警察官とは違うの?」と疑問に思いませんか?
実は岡っ引きの役割を現代の職業に例えると、江戸時代の治安システムがグッと身近に感じられます。
「同心は正社員、岡っ引きは業務委託?」など、会社組織に置き換えるとわかりやすくなりますよ。
この記事でわかること
- 岡っ引きを現代の職業に例えてわかりやすく解説
- 同心・与力との違いを会社組織で比較
- 意外と知られていない岡っ引きの給料システム
- 江戸の治安維持が現代とどう違うか
岡っ引きってどんな人?まずは基本を押さえよう

岡っ引き(おかっぴき)とは、江戸時代に町奉行所の同心に雇われて、犯罪捜査や情報収集を手伝った民間人のことです。
「目明かし(めあかし)」とも呼ばれました。
ざっくり言うと、公務員ではなく、警察の仕事を手伝うアルバイトや業務委託スタッフのようなもの。
正式な武士身分ではありませんでしたが、十手を持つ権限はありました。
なぜ民間人が捜査に?
江戸の人口は100万人を超える大都市でしたが、正式な捜査官(同心)はわずか数十人しかいませんでした。
そこで、地域に詳しい人物を雇って情報網を広げる必要があったのです。
岡っ引きは今で言うとどんな職業?

岡っ引きを現代の職業に例えると、以下のような立場に近いと言えます。
| 江戸時代 | 現代の相当職 | 役割の共通点 |
|---|---|---|
| 岡っ引き | 警察協力者・情報提供者 | 市民目線で情報収集・容疑者の特定協力 |
| 岡っ引き | 探偵・調査員 | 聞き込み・尾行・証拠収集 |
| 岡っ引き | 防犯ボランティア | 地域の治安維持・不審者の通報 |
ただし、江戸時代の岡っ引きはある程度の逮捕権限も持っていたため、現代の民間人よりは権限が強かったと言えます。
現代との最大の違い:逮捕権と十手
現代の防犯ボランティアや情報提供者には逮捕権がありませんが、岡っ引きは十手(じゅって)を持つことで、現行犯や逃亡中の容疑者を捕まえる権限がありました。
十手は「町奉行所の権限を代行する証」のようなもの。
現代で言えば「警察手帳」に近いイメージです。
同心・与力・岡っ引きの違いを会社組織で例えると?

江戸時代の治安維持組織は複雑ですが、現代の会社組織に例えるとスッキリ理解できます。
| 江戸時代の役職 | 現代の会社組織 | 身分 | 給料の出どころ | 主な役割 |
|---|---|---|---|---|
| 町奉行 | 事業部長・支社長 | 武士(旗本) | 幕府 | 治安全体の責任者 |
| 与力(よりき) | 部長 | 武士(旗本) | 幕府 | 事件の指揮・管理 |
| 同心(どうしん) | 課長・係長 | 武士(御家人) | 幕府 | 捜査実務の責任者 |
| 岡っ引き | 業務委託・派遣スタッフ | 平民(町人) | 同心から個人的に支給 | 情報収集・捜査協力 |
| 下っ引き | アルバイト | 平民(町人) | 岡っ引きから支給 | 岡っ引きの手下・雑用 |
つまり、町奉行→与力→同心→岡っ引き→下っ引きという指揮系統でした。
岡っ引きの仕事内容を現代の職業で例えると?

岡っ引きの主な仕事は、町中を歩き回って情報を集めることでした。
具体的な業務内容(現代職業で例えると)
①情報収集=営業マンの情報網構築
盗難・喧嘩・火事などの事件情報を集める。
現代で言えば、営業マンが取引先から情報を集めるイメージ。
②聞き込み=記者・探偵の取材活動
目撃者から話を聞き、容疑者の特定につなげる。
現代のジャーナリストや探偵の調査に近い。
③監視・尾行=探偵の素行調査
容疑者の居場所を特定し、行動を監視する。
現代の探偵業務そのもの。
④逮捕補助=警備会社の現行犯確保
同心と同行して容疑者を逮捕。
現代の警備会社が不審者を確保する場面に似ている。
⑤予防活動=防犯ボランティア
犯罪の前兆を察知して報告。
現代の地域防犯パトロールに近い。
岡っ引きの給料システムは今で言うと?

岡っ引きの収入は不安定でした。
給料の内訳(現代で例えると)
①基本給=少額の固定報酬
同心から月に1〜2両程度(現代で言うと月3〜6万円程度)の固定報酬。
これだけでは生活できません。
②成果報酬=事件解決ボーナス
事件を解決したときの褒美(報奨金)が主な収入源。
現代のフリーランスや営業職の歩合制に似ています。
③裏収入=グレーゾーンの副業
情報提供の見返りに賄賂を受け取ることもありました。
現代で言えば、コンサルタントが情報料を受け取るようなもの(ただし倫理的にはグレー)。
岡っ引きと「目明かし」「下っ引き」の違いは?

岡っ引き=目明かし
岡っ引きと目明かしは、ほぼ同じ意味です。
「目明かし」は「事件を明らかにする(解決する)人」という意味から来ています。
地域によって呼び方が違うこともありました。
下っ引き=岡っ引きの部下
下っ引き(したっぴき)は、岡っ引きの配下で働く人たちです。
現代で言えば、業務委託スタッフ(岡っ引き)が雇うアルバイトのようなもの。
| 役職 | 現代で例えると | 十手 | 給料の出どころ |
|---|---|---|---|
| 岡っ引き | 業務委託・フリーランス | 持てる | 同心から |
| 下っ引き | アルバイト・手伝い | 持てない | 岡っ引きから |
なぜ「岡っ引き」と呼ばれた?名前の由来

由来①「岡に引き上げる」説
犯人を捕まえて「岡(おか=陸地・高台)に引っ張り上げる」ことから「岡っ引き」と呼ばれるようになったという説があります。
江戸は水路が多く、犯人が川や堀に逃げ込むことが多かったため、この表現が生まれたと言われています。
由来②「御掛かり引き」説
同心に「お掛かり(=配属・所属)」して働く「引き(=手引き・案内役)」だから「御掛かり引き」が転じて「岡っ引き」になったというもの。
こちらの方が語源としては有力視されています。
岡っ引きにまつわる意外な話

元犯罪者が岡っ引きに?
岡っ引きには元泥棒や元詐欺師など、過去に犯罪歴がある人も多く雇われました。
理由は、裏社会の人脈とノウハウを活かせるから。
現代で言えば、元ハッカーがセキュリティ会社に雇われるようなものです。
「敵を知るには敵になれ」という発想ですね。
女性の岡っ引きもいた
実は女性の岡っ引きも存在しました。
「岡っ引き女」や「女目明かし」と呼ばれ、主に女性犯罪者の取り調べや、女性しか入れない場所(湯屋など)での情報収集を担当していました。
岡っ引きはいつ頃なくなった?

1874年(明治7年)に警視庁が設置され、正式な警察官が配置されるようになったため、岡っ引きのような民間協力者制度は不要になりました。
現代で言えば、業務委託スタッフだけに頼っていた組織が、正社員を大量採用して内製化したようなものです。
まとめ:岡っ引きと現代社会の共通点と相違点
岡っ引きについて押さえておきたいポイント
- 現代で言うと「警察の民間協力者」「情報提供者」「探偵」に近い
- 正式な武士ではなく、同心に雇われた平民(業務委託スタッフのようなもの)
- 十手を持ち、ある程度の逮捕権限もあった
- 給料は不安定で、事件解決の報奨金が主な収入源(歩合制)
- 与力→同心→岡っ引き→下っ引きという指揮系統
- 元犯罪者や女性の岡っ引きも存在した
- 明治時代に近代警察制度が導入され廃止された
現代に通じるポイント
江戸時代の岡っ引きシステムは、正社員だけでは回らない組織が、外部の専門家や地域の協力者を活用するという発想でした。
これは現代の「業務委託」「フリーランス活用」「地域防犯ボランティア」にも通じる考え方です。
時代は変わっても、「組織の外の力を借りる」という知恵は今も昔も変わらないのかもしれませんね。
関連記事
- 同心とは?現代の警察官に例えてわかりやすく解説
- 【図解】江戸時代の身分制度を会社組織で例えるとこうなる!
- 十手の役割とは?現代の警察手帳に例えて解説
- 与力と同心の違いを現代の役職で例えてスッキリ理解!