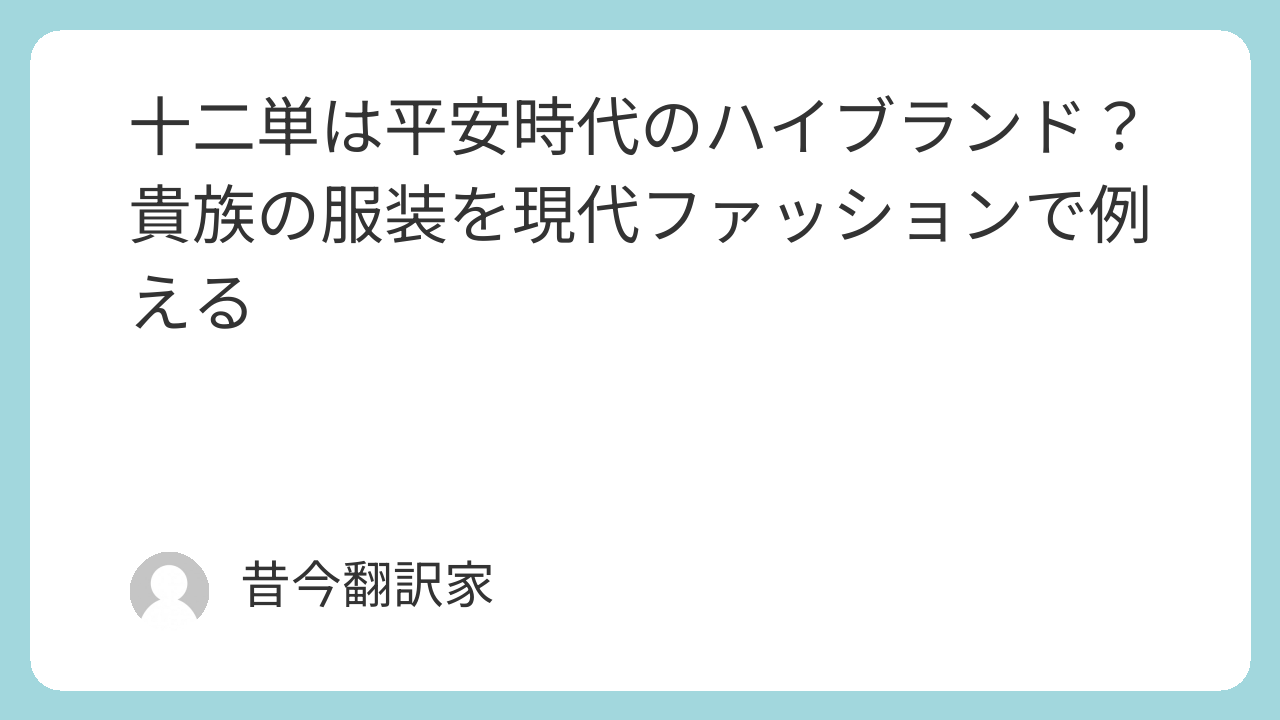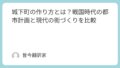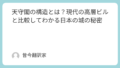平安時代の優雅な装いを現代人にも身近に感じられる形で解説します。
十二単(じゅうにひとえ)という貴族女性の正装は単なる衣服ではなく、現代のハイブランドファッションと同じような社会的ステータスを表す重要な手段でした。
この記事では、十二単の仕組みから色選びの重要性、そして現代のファッションブランドに例えた価値まで、平安貴族のファッション事情を深掘りします。
「12枚も重ねて暑くないの?」という素朴な疑問から、「エルメスのバーキンのような希少価値」を持つ色彩の世界まで、1000年以上前のファッションセンスが現代に通じる意外な共通点をお楽しみください。
この記事でわかること
- 十二単の重ね着の仕組みと現代ファッションとの共通点
- 平安貴族のファッションが持つ「ブランド価値」の正体
- 色選びが命!現代のカラーコーディネートとは比べ物にならない色彩センス
読むのに必要な時間:約7分
十二単って実際何枚着てるの?
「十二単」と聞くと「12枚も着るの!?」と驚く方が多いのですが、実際には12枚すべてを常に着ていたわけではありません。
十二単とは、正式には「着物の種類が12種類ある」ということを意味しています。
現代のファッションで例えるなら、「フルコーディネートセット」のようなもの。
トップス、インナー、ボトムス、カーディガン、コート…と、全部揃えても毎日全部着るわけではありませんよね。
十二単も同じで、季節や場面に応じて必要な衣を5〜10枚程度重ねるのが一般的でした。
基本的な重ね着の順番は
- 肌着(今でいうインナーウェア)
- 単(ひとえ)(基本の着物)
- 袿(うちき)(上着のような役割)
- 表着(うわぎ)(メインの装飾的な着物)
- 唐衣(からぎぬ)(軽い上着)
- 袿(うちき)(さらに重ねる上着)
- 表袴(うわばかま)(装飾的なスカート部分)
ここまでのポイント
十二単は12種類の衣服の総称で、実際はTPOに合わせて重ね着を調整していました。
なぜあんな暑そうな服を着ていたの?
「夏でもあんな重そうな服を着て、暑くなかったの?」というのは多くの人が抱く疑問です。
結論から言うと…暑かったです!特に夏場は相当な重労働だったでしょう。
でも、平安貴族にとって十二単は、現代人がブランドバッグを持ったり、高級時計を身につけたりするのと同じなんです。
例えるなら
- 現代の高級ハイヒール:見た目は美しいけど、実は足が痛い
- セレモニーでのタキシード:動きにくいけどかっこいい
- コルセット:呼吸が苦しいけど、体のラインが美しく見える
平安貴族の女性たちは「美しさ」と「社会的立場の表現」のために、ある程度の不快感は我慢していたわけです。
また、当時の貴族の女性たちは現代のように外出する機会も少なく、主に屋内で過ごしていました。
ここまでのポイント
十二単は確かに暑く不便でしたが、美しさとステータスのシンボルとして、現代のファッションアイテムと同じ社会的役割を果たしていました。
平安貴族のファッションブランド事情
平安時代に「ルイ・ヴィトン」や「グッチ」はなかったですが、産地や織り手によるブランド価値は確かに存在しました。
例えば
- 高級唐織物:現代のハイブランド海外製品のような扱い
- 紫織部(むらさきおりべ):特定の高級工房で作られた布(現代で言えばエルメスのような存在)
- 綾(あや)・錦(にしき):特殊な織り方をした高級素材(現代のカシミヤやシルクのような高級素材)
「あの方は○○の織物を着ているわ」と噂されるのは、現代で「彼女、またシャネルの新作バッグ買ったみたい」と言われるのと同じだったのです。
特に中国(唐)からの輸入品は特別な価値があり、「限定海外ブランド」のような扱いでした。
現代で言えば、パリコレで発表されたばかりの最新デザインを誰よりも早く着ているような感覚です。
ここまでのポイント
平安時代にもファッションの「ブランド価値」があり、どこの織物を使うかは現代のブランド選びと同様に重要な社会的メッセージでした。
「色」で語る平安ファッション
現代でも「この色、私に似合う?」と気にしますが、平安時代の人々の色へのこだわりはその比ではありません。
十二単の最大の見せ場は「襲(かさね)の色目」、つまり重ね着した時に袖口や裾から見える色の組み合わせでした。
これを現代に例えると
- ユニクロやZARAでコーディネートを考えるレベル:初心者
- パリコレでトータルコーディネートを考えるレベル:中級者
- 平安貴族の色彩センス:超上級者(プロ中のプロ)
平安時代には「梅重(うめがさね)」「松皮(まつかわ)」など、「この季節にはこの色の組み合わせ」という決まりがあり、さらに色の組み合わせには美意識だけでなく、和歌の世界観や季節感、時には政治的メッセージまで込められていました。
例えば
- 藤色+薄紫:初夏の優美さを表現(5月頃のコーディネート)
- 紅葉襲:秋の情緒を表す色の組み合わせ(10月頃の定番)
ここまでのポイント
平安貴族のファッションでは「色」が最重要要素で、その選び方には現代のファッションコーディネートを遥かに超える複雑なルールと意味がありました。
十二単、着るのにどれくらい時間がかかるの?
「朝起きて十二単を着て、さあ出かけよう!」なんてことはできません。
十二単の着付けには複数の女官(メイド)が必要で、かなりの時間がかかりました。
現代に例えると
- 普段の服を着る:自分でサッとできる(5分以内)
- スーツやフォーマルドレス:少し手間がかかる(15分程度)
- 十二単を着る:まるでハリウッド女優がアカデミー賞授賞式の準備をするレベル(最低30分~1時間以上)
着付けの手順は
- まず下着を着る
- 単衣を着る
- 重ね衣を一枚ずつ順番に着ていく
- 袖や裾の出具合を調整する(これが最も重要!)
- 髪型を整える(これもまた大変な作業)
特に重要なのは衣の重なり方と見え方の調整。
現代のスタイリストがレッドカーペット前にセレブの服の皺一つまでチェックするのと同じように、女官たちは十二単の「見え方」に神経を使いました。
ここまでのポイント
十二単の着付けは現代のセレブの特別なイベント準備のように、手間と時間がかかる一大事業でした。
現代ファッションブランドで例える十二単の価値
平安時代の十二単一式の価値を現代のファッションブランドで例えてみましょう。
十二単の各部位と現代ブランドの対比
- 表着(うわぎ)→ エルメスやディオールのオートクチュール(メインの見せ場となる最高級品)
- 唐衣(からぎぬ)→ シャネルのジャケット(格式の高さを示す品)
- 単(ひとえ)→ プラダのシルクドレス(基本だけど高品質)
- 裳(も)→ ルイ・ヴィトンの限定品(格式を示す重要アイテム)
- 小物類 → カルティエやティファニーのアクセサリー(細部までこだわる贅沢さ)
十二単一式の総額は、現代の価値に換算すると数千万円クラスになることも。
これは現代のセレブがメットガラなどの特別なイベントで身につける衣装の総額に匹敵します。
特に、「紫」や「藤色」といった特定の染料は当時とても貴重で、現代で言えばエルメスのバーキンやケリーバッグのように「手に入れるのが難しい」希少価値がありました。
ここまでのポイント
十二単は単なる衣服ではなく、現代の超高級ブランドコレクションに匹敵する価値と社会的意味を持っていました。
平安貴族のファッショントレンド最前線
「平安時代だからファッションに流行なんてなかったでしょ?」と思うかもしれませんが、それは大間違い!
平安時代にも明確なトレンドが存在し、それを追いかける「トレンド派」と伝統を重んじる「クラシック派」がいました。
現代のファッション界に例えると
- 最新トレンドを追う人 vs. クラシックなスタイルを好む人
- ファストファッションの新作をチェックする人 vs. 長く着られる定番品を選ぶ人
- 平安版インスタグラマー(誰よりも早く新しいスタイルに挑戦)vs. 平安版オールドマネー(家系代々の伝統的な装い)
特に、中国(唐)や朝鮮半島からの新しいデザインは、現代のパリやミラノからの最新トレンドのような扱いでした。
藤原道長のような超有力者の娘や妻が着る色や柄は、現代のセレブやロイヤルファミリーのファッションと同じく、すぐに真似されるトレンドになったのです。
まとめ
まとめると…
- 十二単は常に12枚着るわけではなく、TPOや季節によって5〜10枚程度の調整が一般的
- 当時の平安貴族にとって十二単は現代のハイブランドファッションと同じ社会的ステータスを表すもの
- 色の組み合わせが最も重要で、現代のファッションよりもさらに複雑で意味を持つ色彩センスが求められた
- 十二単一式は現代価値で数千万円相当もの価値があり、着るには複数の侍女と長い時間が必要だった
- 平安時代にも明確なファッショントレンドがあり、最新の流行を追う人と伝統を重んじる人の対立は現代と変わらない
今の時代にも通じる教訓:ファッションが持つ「社会的メッセージ性」は時代を超えて変わらず、衣服は単なる体を覆うものではなく、自分の立場や価値観を表現する重要な手段であることが平安時代から続いています。