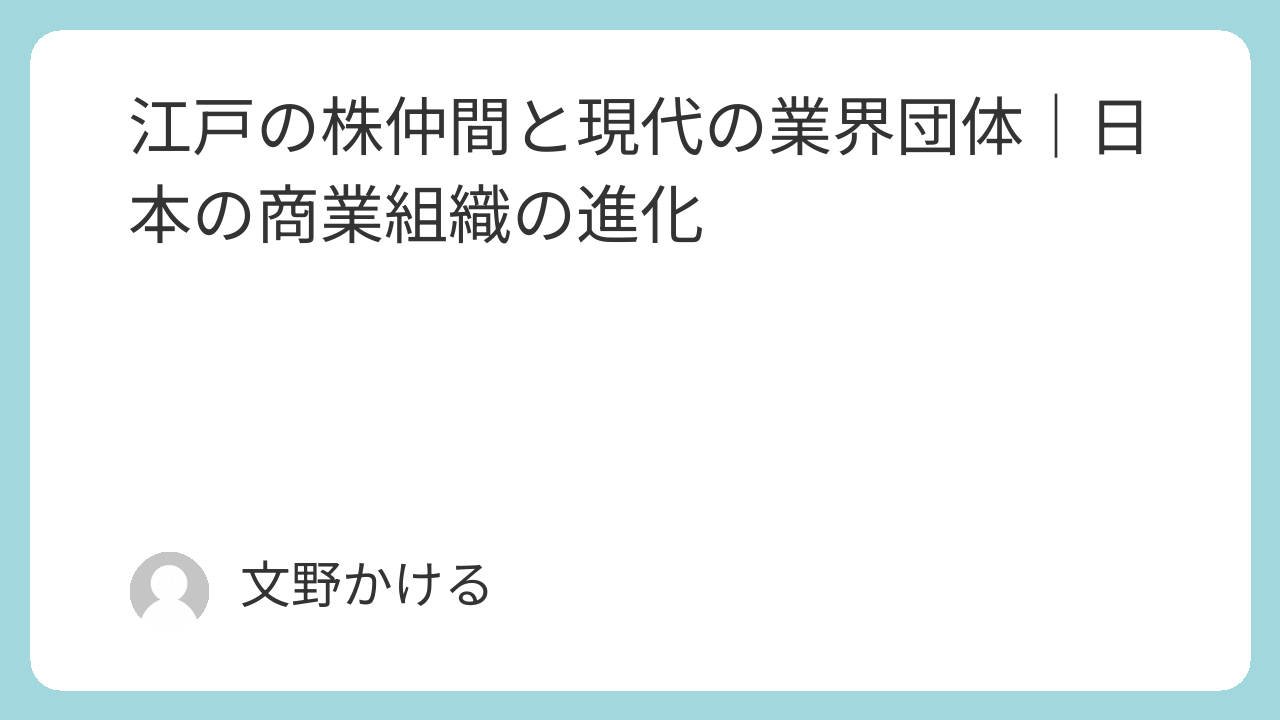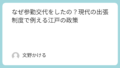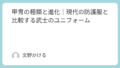「業界団体って昔からあったの?」「江戸時代の商人ってどうやって商売してたの?」こんな疑問を持ったことはありませんか?
実は現代の業界団体や商工会議所のルーツは、江戸時代の「株仲間」にまでさかのぼるんです!
この記事でわかること
- 江戸時代の株仲間の仕組みと現代の業界団体との共通点
- 商人たちがなぜ「株」という独占権を欲しがったのか
- 株仲間から現代の商工会議所までの日本の商業組織の進化
読むのに必要な時間:約8分
株仲間って何?現代で例えると?
「株仲間(かぶなかま)」とは、江戸時代に同じ商売をする商人たちが集まって作った組合のようなものです。
今でいう「○○業界団体」や「××協会」のようなものと考えるとわかりやすいでしょう。
例えば現代なら「日本玩具協会」「全国スーパーマーケット協会」「日本料理店協会」などがありますが、江戸時代にも「呉服問屋仲間」「米問屋仲間」「魚河岸仲間」などが存在していました。
今のコンビニ本部とフランチャイズ店の関係に少し似ています。
加盟するには「株」という参加権(フランチャイズ権のようなもの)を買う必要があり、その代わり商売の独占権や様々な特権が得られました。
ここまでのポイント
株仲間は同業者が集まった組合で、現代の業界団体の先祖のような存在です。
なぜ商人たちは株仲間を作ったの?
商人たちが株仲間を作った理由は主に3つあります。
まず第一に、商売の独占権を得るためです。
株仲間に入れば、その業種での商売を安定して行う権利が保証されました。
現代で言えば「営業許可証」と「業界での席」を同時に手に入れるようなものです。
第二に、同業者間の過当競争を防ぐためです。
今でいうカルテルのような価格協定や市場分割を行っていました。
これにより、商人たちは安定した利益を確保できました。
第三に、相互扶助の仕組みを作るためです。
誰かが火事や災害で店を失った時、病気になった時などに助け合う「保険」のような機能もありました。
ここまでのポイント
株仲間は商売の独占と安定、そして相互扶助のために作られました。
株仲間の「株」って株式会社の株とは違うの?
「株」という言葉が紛らわしいですが、株仲間の「株」と現代の株式会社の「株」は別物です。
株仲間の「株」は、特定の商売をする権利や資格そのものを指します。
今で言えば「タクシーの営業許可」や「酒類販売免許」のようなものです。
この権利は売買できましたが、利益の配当を受ける現代の株式とは性質が違います。
江戸時代中期になると、株の価格は高騰し、一株で数百両(現代の数千万円相当)するものもありました。
そのため子どもに相続させたり、親戚や弟子に譲渡したりすることも一般的でした。
現代のタクシー会社が持つ「営業許可証」が高値で取引されるのに少し似ています。
特に東京などの大都市では、タクシーの営業権(いわゆる「プレート」)が数百万〜数千万円で取引されることがあります。
ここまでのポイント
株仲間の「株」は商売の権利そのものを表し、現代の株式とは異なります。
株仲間はどんな活動をしていたの?
株仲間の主な活動は5つありました。
- 価格統制: 商品の価格を業界全体で一定に保つ(現代の価格カルテル)
- 品質管理: 粗悪品の流通を防ぎ、業界全体の信用を守る
- 新規参入の制限: 「株」を持たない商人の営業を排除する
- 相互扶助: 火災や災害時の援助、病気の際の見舞金など
- 行政との窓口: 幕府や藩への税金納入、規制交渉の窓口となる
例えば、江戸の「呉服問屋仲間」は、高級着物の品質基準や価格設定を決め、それを守らない業者を排除していました。
これは現代のブランド業界団体が模倣品対策をするのと似ています。
今のJASマークや業界自主規制のような品質保証の仕組みも、実は株仲間の時代からあったのです。
ここまでのポイント
株仲間は価格統制、品質管理など、現代の業界団体とよく似た活動を行っていました。
株仲間が禁止された理由は?
1841年、江戸幕府は「株仲間解散令」を出し、いったん株仲間を禁止しました。
これは、株仲間による独占が物価高騰を招いたためです。
現代の独占禁止法や公正取引委員会による規制と似た発想です。
しかし、この禁止はうまくいかず、1851年には復活が認められました。
そして最終的に、明治4年(1871年)に明治政府が「株仲間の特権を廃止する」という太政官布告を出し、株仲間は完全に廃止されました。
これは、現代でいえば「規制緩和」や「市場開放」のような政策です。
明治政府は西洋式の自由経済を導入するため、伝統的な独占組織を解体したのです。
ここまでのポイント
株仲間は独占による弊害から幕末に一時禁止され、明治維新後に完全に廃止されました。
現代の業界団体との共通点と相違点
株仲間と現代の業界団体を比較してみましょう。
共通点:
- 同業者の利益を守る
- 業界の品質基準を設ける
- 政府との交渉窓口になる
- 会員同士の情報交換の場になる
- 相互扶助の機能を持つ
相違点:
- 株仲間は参加が事実上「強制」だったが、現代は任意加入
- 株仲間は営業の独占権があったが、現代の団体にはない
- 株仲間は価格統制が主な活動だったが、現代は違法(カルテル規制)
- 現代の団体は政策提言や啓発活動など社会的役割が大きい
現代の業界団体を会員制クラブとすれば、株仲間はフランチャイズチェーンに近い強制力を持っていました。
株を持たなければその商売ができない仕組みだったのです。
ここまでのポイント
基本的な目的は似ていますが、現代の業界団体は強制力や独占性が弱まっています。
株仲間から現代の商工会議所への進化
株仲間が禁止された後、日本の商業組織はどう変わったのでしょうか?
その進化の過程を見てみましょう。
- 1871年:株仲間廃止
- 1878年:東京商法会議所(現在の東京商工会議所の前身)設立
- 1890年代:各業種別の同業組合法制定
- 1922年:商工会議所法制定
- 戦後:独占禁止法により、カルテルなどの活動が規制される
明治時代の商法会議所は、株仲間の相互扶助機能と政府との交渉窓口機能を引き継ぎました。
しかし、価格統制や参入制限といった独占的機能は失われていきました。
この変化は、SNSの出現でコミュニケーションの形が変わったのに似ています。
基本的な「つながる」という機能は同じでも、ルールや影響力が大きく変わったのです。
ここまでのポイント
株仲間の伝統は形を変えながら現代の商工会議所や業界団体に受け継がれています。
まとめ
まとめると…
- 江戸時代の株仲間は現代の業界団体の先祖であり、商人たちが集まって商売の独占権を得るための組織だった
- 株仲間の「株」は商売する権利そのものを指し、現代の株式会社の株とは異なる
- 株仲間は価格統制、品質管理、相互扶助など、現代の業界団体と似た機能を持っていた
- 独占による弊害から明治時代に廃止され、より自由な形の商法会議所や同業組合へと進化した
- 現代の業界団体は株仲間と比べて強制力や独占性が弱まったが、基本的な目的や機能は受け継がれている
江戸時代の株仲間から現代の業界団体まで、日本の商業組織は時代とともに進化してきました。
しかし「同業者が集まって互いの利益を守る」という基本的な発想は、300年以上たった今でも変わっていません。
現代社会で当たり前のように存在する業界団体も、その歴史をたどれば江戸時代の商人たちの知恵と工夫にたどり着くのです。
歴史は繰り返すというより、形を変えながら続いているのかもしれませんね。